息子の困りごとに限界を感じた日々
小学校に入学した息子の様子に、私は焦りと不安を感じていました。
教室の中を歩き回る、授業中に勝手に教室を出て行ってしまう。筆箱は毎日空っぽで、持ち物は持って帰ってこない。連絡帳も書かれておらず、担任の先生に言われて初めて、息子専用の段ボールを作成され溜まった落とし物の存在を知った時は、正直ショックでした。
さらに、毎日のように起きるトラブル。
同級生に手を出してしまう、蹴ってしまう、叩いてしまう。ある日は、上級生とケンカになり、止めに入った子の顔を思わず叩いてしまい、鼻血が出てしまったという連絡が。私は震える手で学校からの謝罪電話を受け取りながら、ついに親として呼び出されることになりました。
このままでは、息子も私もつぶれてしまう。
それが私の正直な気持ちでした。
「もし何もなければそれでいい」夫への相談
ある晩、思い切って夫に話しました。
「発達検査を受けさせたいと思ってる。もし何もなければそれでいい。だけど、もし何かあるのなら、ちゃんと理解してあげたい。私たちも、先生たちも。」
夫は最初、戸惑った表情を浮かべました。「男の子なんてそんなもんだろ」と言っていたのも事実です。でも、この数カ月で息子の行動に限界を感じていたのは、夫も同じでした。
少しの沈黙のあと、「わかった。一度受けてみよう」とうなずいてくれたとき、涙がこぼれました。やっと、一緒に息子の“困りごと”と向き合える気がしたのです。
子育て支援課への相談と検査までの流れ
次の日、市の子育て支援課に電話をしました。勇気がいりましたが、窓口の方はとても丁寧に話を聞いてくれました。
「まずは、臨床心理士による発達検査(WISC)を受けましょう」と提案され、流れを説明してくれました。
ただ、精神科医の診察予約はすでにいっぱいで、最短でも半年後だと言われました。ショックでした。早く結果が知りたい気持ちと、現実とのギャップに戸惑いましたが、それでも「やっと一歩踏み出せた」と少しだけ安心しました。
夫の心の変化と、家族としての決意
それからというもの、夫は少しずつ、息子の行動をただ叱るのではなく、「なぜこんなことをしたんだろう?」と一緒に考えるようになってくれました。
「先生はどう対応してるの?」
「こういう場合、どうするんだろう?」
そんな言葉が夫の口から出てくるようになり、私たちは夫婦として、親として、同じ方向を向き始めたのです。
一番つらいのは、息子自身だった
今ならわかります。
困っていたのは、息子だったのです。
「悪い子」だったのではなく、「困っている子」だった。うまく伝えられない、自分をコントロールできない、そんな自分に苦しんでいたんだと思います。
私たち大人がそれに気づくまで、息子はずっと、ひとりで戦っていたのかもしれません。
最後に:迷っているあなたへ
発達検査を受けることに、何の抵抗もありませんでした。検査は決して“障害を見つけるため”だけのものではなく、“支援の糸口を見つけるため”のものです。
何もなければそれでいい。でも、もし何かがあるのなら、早く気づいてあげたい。そう思えたとき、迷いはなくなりました。
今、同じように悩んでいるお母さんがいたら、どうか一人で抱え込まないでください。子どもの“困りごと”には、きっと理由があります。そして、その理由がわかれば、対応する方法も見つかります。
あなたと、あなたの大切なお子さんが、少しでも心穏やかに過ごせますように。
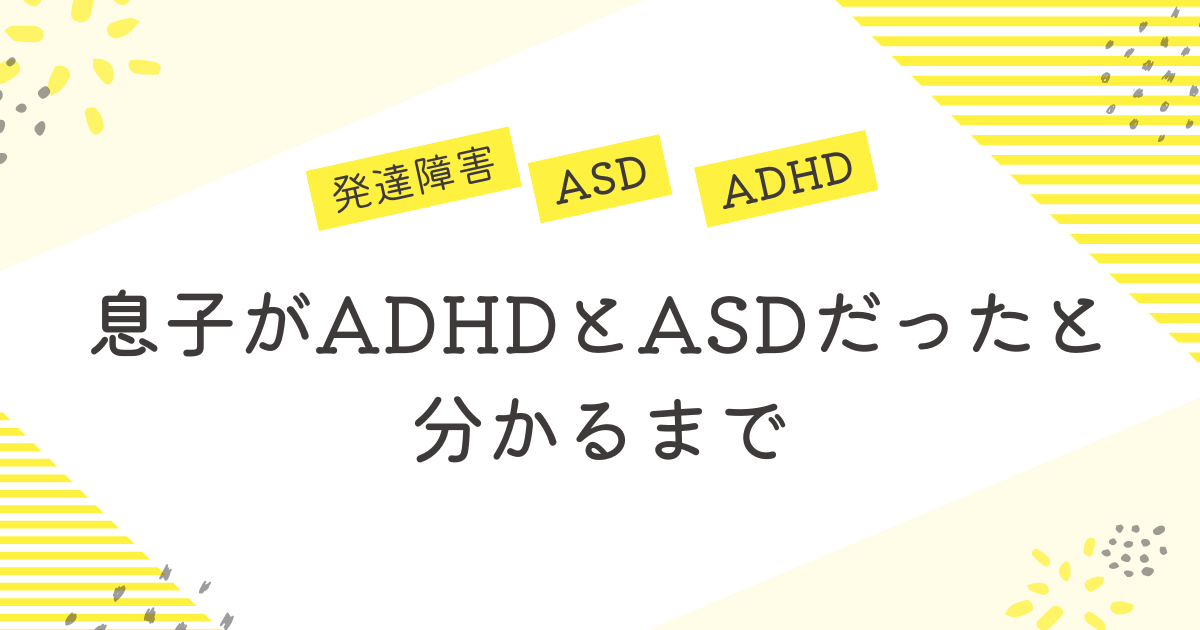
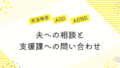
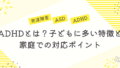
コメント